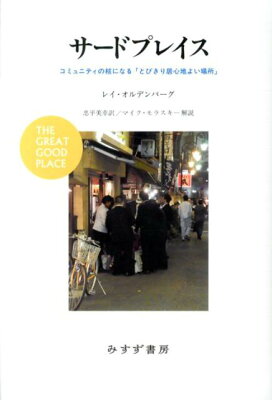書籍「サードプレイス」ってどんな本
自宅でもない、学校でも職場でもない、居心地の良い第三の場所…つまりサードプレイスとは何かを理解するために、1932年生まれのアメリカの都市社会学者レイ・オルデンバーグが1989年に刊行した「The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and Other Hangouts at the Heart of a Community」の翻訳書「サードプレイス〜コミュニティの核になる『とびきり居心地よい場所』〜」を読んでみました。インフォーマルな公共生活の欠如という当時のアメリカが抱える問題への解決策として、サードプレイスの醸成が主張されています。
サードプレイスの8つの特徴やサードプレイスが個人や社会にもたらす恩恵、サードプレイスの実例、サードプレイスを取り巻く諸問題など、全480ページにまとめられています。

インフォーマルな公共生活の中核的環境
サードプレイスとは何か、オルデンバーグは「インフォーマルな公共生活の中核的環境」と位置付けています。家庭や仕事場が制度上ガッチリとしたフォーマルな領域だとすれば、サードプレイスはもっと個人のパーソナリティに寄った自由な領域と言えます。
サードプレイスというのは、家庭と仕事の領域を超えた個々人の、定期的で自発的でインフォーマルな、お楽しみの集いのために場を提供する、さまざまな公共の場所の総称である。
サードプレイス〜コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」P59
とびきり居心地よい場所
原著は「The Great Good Place」ですので、日本語訳すると「とびきり居心地よい場所」となります。副題に例示でしょうか、カフェ、コーヒーショップ、本屋、バー、ヘアーサロンなどが謳われています。
それぞれ家庭でも仕事場でもない、まちなかにあるアジールというか、健康で文化的な生活を送る上で必要になるような場所です。原著の表紙からも、著者が「とびきり居心地よい場所」つまりサードプレイスをどのようにイメージしているかが伝わってきます。
サードプレイスの8つの特徴
書籍「サードプレイス」では、世界各地のサードプレイスに共通する8つの特徴があると指摘しています。
世界各地のサードプレイスには、共通する本質的な特徴がある。時間と文化の枠を越えて実施されたある調査のように、アラビアのコーヒーハウス、ドイツの居酒屋(ビアシュトゥーべ)、イタリアの食堂(タベルナ)、アメリカ西部の昔ながらの雑貨屋、スラム街のバーには類似性が見てとれる。
サードプレイス〜コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」P64
1 中立の領域
強制されて渋々行くような場所でもなければ、行ったからには何かしなければいけないわけでもない、そんな中立の領域です。個人の都合に合わせて自由に出入りができるニュートラルな場所です。
2 人を平等にする
職場の上司と部下、学校の先生と生徒といった上下関係や主従関係とは無縁の場所です。大手企業や行政の役職などの肩書や社会的地位の高さは、ここではフラットになります。ありのままの個人として認められる場所です。
3 会話が主な活動
サードプレイスでの活動は会話がメインです。そこでのおしゃべりが素敵であること、活発であること、魅力的であることが交流の喜びとなります。まちで住んだり働いたり学んだり遊んだりしている多様な人たちが、フラットな関係性で会話できる場所です。
4 利用しやすさと便宜
昼夜を問わずほとんどいつでもきっと知り合いがそこにいると確信して一人で出かけていける場所です。家庭や仕事、学校という優先的かつ基本的なルーティンの合間や前後に、ふらっといつでも気軽に立ち寄ることができます。近場にある、ということが重要です。
5 常連
新参者を気持ちよく歓迎し受容する、場所を熟知して特色ある雰囲気を作ってくれる常連の存在が重要です。新参者から見ると、サードプレイスの集団は同質的で排他的、閉鎖的に感じられがちです。常連が固定化するのではなく、新たな常連がたくさん生まれるようにする必要があります。
6 目立たない存在
場所としての飾り気のなさや地味さもポイントになります。利益を出すことを優先する一等地沿いのお店とは違い、控え目かつ慎ましい雰囲気があり、それが外観上も反映されています。日常生活のごく普通のひとこまにすぎない場所であり、一見するとみすぼらしい感じがします(ただし、内部は清潔が保たれている)。
7 その雰囲気には遊び心がある
目立っていようといまいと遊びの精神を重視します。定まった活動がない即席の集まりかもしれないけれど、誰もが思わず長居してしまうという体験や衝動がある場所です。
8 もう一つのわが家
プライベートな場所である家のように居心地の良い場所、という意味です。パブリックな場所であるサードプレイスを一人称の所有格を使って指し示したり(○○は私たちのたまり場だ)、元気を取り戻せたり心が休まったり、精神的な心地よさと支えを与える場所です。
サードプレイスの理念
以上ざっくりと見てきました。正直この8つの特徴は著者が考える理念(理想)であり、日本の各地のまちや地域にそのまま当てはまるとは思えません。行きつけの喫茶店やカフェでボーッとお茶したり静かに本を読んだり、公園や河川敷に座って空や川を眺めたり、定期的に行く床屋や美容室でちょっとしたおしゃべりを楽しむ、など特段アクティブにならなくても、それぞれの人にとってのサードプレイスは既に存在しているはずです。
しかし私は、まちや地域にサードプレイス的な場所が非常に少ないと感じています。サードプレイス的な場所がもっと増えることで多様な人同士の交流機会が増えたり、個人の健康につながったり、経済効果や社会問題の抑止や解決にまでつながると考えています。ここらへんの仮説はイノイチサードプレイスプロジェクトという社会実験的な取組で検証していけたらと思います。
(参考)
『サードプレイス』はいかなる場所か?訳書で徹底議論|リーディングクラブ#4 | ソトノバ | sotonoba.place
知ってます?「サードプレイス」の本当の意味。8つの条件をクリアして、社会的・経済的価値を、より高める。次の時代のカギはココ!|大西正紀/GroundLevel & 喫茶ランドリー|note
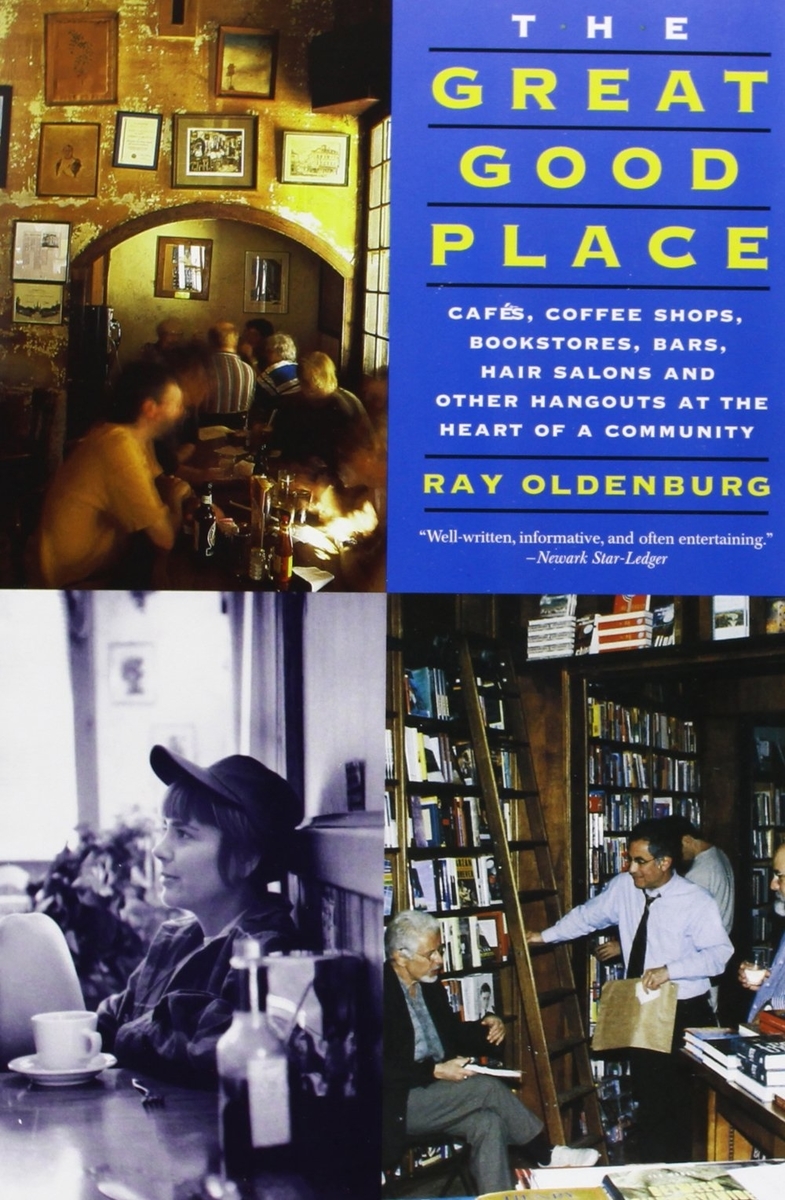 (出典:
(出典: